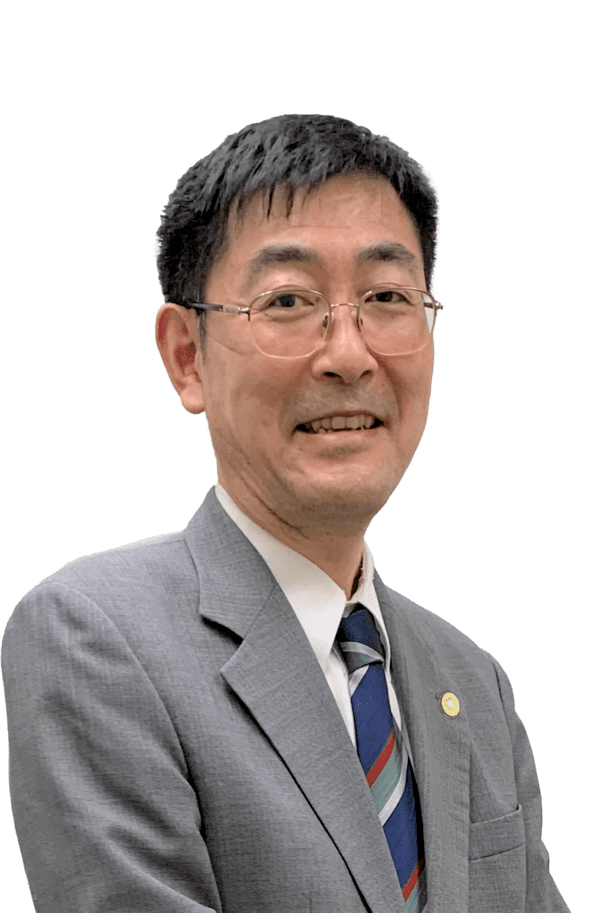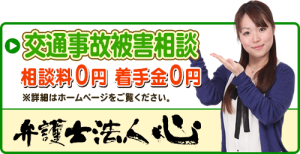- トップ
- ブログ
ブログ
被害に遭った車両が経済的全損とされた場合の賠償請求について
1 はじめに
事故で車両が損傷する被害を受けた場合、これに対する賠償については、修理費と、事故当時の車両価格を比較して、どちらか安い方を賠償すれば足りるとされています。
上記の考えを示した最高裁の判例もあります。
修理費と車両価格のどちらか安い方を賠償すれば足りるとされる理由ですが、例えば、修理費が100万円、車両の値段が50万円とされた場合、100万円の修理費を支出しなくても、同じ車両を50万円で調達すれば、事故前の状況に戻るとの考えによるものです。
また、上記のように、車両価格が修理費を下回る場合、この状態を「経済的全損」といいます。
2 経済的全損とされた場合の買替費用について
車両を買い替える場合、車両本体に対する費用(支出)のほかに、新たに購入した車両の登録費用など、車両本体とは別の費用が発生します。
経済的全損とされた場合、車両を修理するのではなく、買い替えることが前提になります。
このため、経済的全損とされた場合、車両本体の価格の費用のほかに、車両の登録手続費用など、買い替えに伴い発生する費用も賠償の対象となります。
3 車両価格の調べ方について
一昔前までは、レッドブックと呼ばれる、中古車価格をまとめた本に記載された車両の価格を賠償額の基準としていました。
しかし、昨今は、グーネット、カーセンサーなどの中古車のサイトが複数あり、車両価格を容易に調べることができます。
具体的には、車種、初度登録年、走行距離、車両のグレードを入力すると、同種の車両が表示されます。
サイトでは、本体価格と、本体価格と諸費用を含めた購入価格の2つが表示されますが、賠償額の算定に当たっては、本体価格(税込)が基準となり、この平均値を賠償額としています。
相手方から示された車両価格が低すぎたり、正しいか疑問に思ったときは、中古車のサイトにて確認することをお勧めします。
4 買替費用の賠償請求について
買い替える車両を注文し、その注文書・見積書に記載された登録費用・登録申請手数料などの賠償を請求することになります。
事故に遭った車両に、コーティングが施されていたり、カーナビが設置されていたのであれば、買い替えにより購入した車両に対するコーティング、カーナビの移設を求めることもできます。
ただし、被害者が加害者に請求できるのは、あくまで事故に遭ったのと同種の車両を購入することを前提とした費用です。
このため、被害に遭った車両が中古車であるのに、新車購入の費用を請求することはできません。
被害に遭った車両が軽自動車であれば、軽自動車購入の費用が基準となるため、これよりも高額となる、普通自動車購入のための費用を請求することも許されません。
5 修理・買替の選択について
これまで使用していた車両に愛着を感じているなどして、経済的全損とされた場合でも、被害に遭った車両を修理して、使用を続けたいと考える方も中にはいらっしゃいます。
このような場合、「経済的全損でも修理しても良いか」と尋ねられることがあります。
また、「修理可能だが、事故に遭った車両には乗りたくないので、買い替えたい。」という方もおります。
経済的全損とされた場合、逆に修理にて賠償することになった場合、被害者は、修理・か買替かの選択についても、制約を受けてしまうのでしょうか。
上記に対する答えですが、修理と買替のいずれによるかは、被害者において、自由に選択できます。
修理とするか、買替とするかの問題は、事故の相手方からの賠償額を決めるための基準にすぎません。
差額は被害者の負担となりますが、経済的全損とされた場合でも、被害者が修理することを選択し、修理することができます。
6 車両保険と対物超過特約について
車両保険の契約内容にもよりますが、買替を前提とした場合、車両保険から支払を受けたほうが、相手方から賠償を受けるよりも有利な結果を得ることができる場合があります。
車両保険に加入している場合は、相手方からの賠償額と、車両保険からの保険金について、必ず比較して、有利な方を選択するようにしてください。
また、相手方の保険に「対物超過特約」が付いている場合は、「車両価格に50万円を足した金額まで」といった制限はありますが、経済的全損の場合でも、修理費相当額の賠償を受けることができる特約もあります。
これを対物超過特約といいます。(一部の保険会社(損害保険ジャパン、SOMPOダイレクト)では、特約の名称を「対物全損時修理差額費用特約」としています。)
ただし、対物超過特約が適用されるためには、実際に修理することが必要であり、修理をしないで修理費のみ請求することはできません。
7 おわりに
事故に遭った車両に対する賠償を巡っては、様々な問題が発生することがあります。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
人身傷害保険と賠償請求について
1 はじめに
交通事故の示談交渉で、時々、事故の相手方が契約する保険会社との間で問題となるのが、「被害者が、先に被害者が加入している人身傷害保険から支払を受けた場合、これを過失相殺をした後の損害額から全額差し引いてもよいか」という点です。
また、被害者が契約している保険会社から人身傷害保険の支払をしてもらおうとしたところ、「相手方から先に支払ってもらってください。」と言われて問題となることもあります。
上記2つの保険会社の言い分は、先に結論をお伝えすると、いずれも誤りとなります。
2 人身傷害保険について
人身傷害保険は、自動車保険の任意保険の特約の一つです。
保険会社によって、人身傷害特約・人身傷害保険と呼び方は異なりますが、いずれも同じ種類の保険です。
事故により負傷したり死亡するなどした際、被害者が契約している保険会社が、治療費や慰謝料などを保険契約に従い支払ってくれることが、人身傷害保険の内容となります。
治療費や慰謝料は、事故の相手方から賠償金として受け取ることができます。
しかし、受け取るためには示談交渉や裁判を経る必要があるため、受け取りまでに時間がかかります。
また、相手方に資力が無いため、賠償金の支払いを全く受けることができないということもあります。
このようなとき、人身傷害保険から支払をうけることで、上記の問題を解決することができます。
3 人身傷害保険からの支払分を賠償額から差し引くことについて
人身傷害保険からの支払内容は、治療費・慰謝料など、事故の相手方から被害者に賠償すべき項目と重なります。
このため、人身傷害保険から支払を受けた場合、事故により発生した損害から、人身傷害保険からの支払分を差し引く必要がありますが、過失相殺がない事案(被害者側が無過失の事案)と、過失相殺が発生する事案(被害者にも過失がある事案)とでは、差し引く範囲が異なります。
過失相殺がない事案では、損害全体から人身傷害保険からの支払分を差し引き、残りを相手方に請求することになります。
これに対し、過失割合が発生する場合、人身傷害保険からの支払は、まず過失相殺により減額される分に充当し、これを超える分を相手方からの賠償額(過失相殺後尾賠償額)から差引き、残りを相手方に賠償することになります。
例えば、損害合計額が100万円、被害者の過失割合が2割であり、相手方が賠償すべき金額は80万円のときに、人身傷害保険から30万円が支払われた場合、30万円は次のように充当されます。
まず、過失割合により減額される20万円の部分に充当します。
次に、残りの10万円(人身傷害保険から支払われる30万円-先ほどの充当分20万円)を、相手方が賠償すべき賠償金80万円の部分に充当します。
この結果、相手方は70万円の賠償をすればよいことになります。
また、被害者は、人身傷害保険からの保険金30万円と、相手方からの賠償金70万円の合計100万円を得ることができ、過失相殺がないのと同じ金額を得ることができます。
なお、相手方は、被害者との間では70万円の支払となりますが、残り10万円については、人身傷害保険を支払った保険会社に支払うことになるため、結局、もとの80万円の賠償をすることになります。
以上のとおり、過失相殺が発生する事案の場合、人身傷害保険は、過失割合で減額される部分に先に充当されるので、相手方が賠償すべき金額(過失相殺により減額された後の賠償額)から人身傷害保険からの支払分全額を差し引くことは、誤りということになります。
4 人身傷害保険からの支払と相手方からの支払の順番について
事故により治療費の負担が生じ、この支払を請求する際、人身傷害保険・相手方のいずれに請求すべきかについて、請求の順番を定めている保険会社はありません。
このため、被害者としては、いずれにも請求することができます。
人身傷害保険に支払を請求したときに「先に相手方から支払ってもらってください。」とすることは、保険の契約内容に反する依頼となります。
5 まとめ
保険からの支払を巡っては、事案によって問題が発生することがあります。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
労災保険の使用について
1 はじめに
事故の加害者が被害者に対して賠償義務を負い、かつ、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は、加害者が契約している任意保険会社から、治療費、休業損害などの支払を受けることができます。
しかし、会社などにお勤めの方が、通勤途中(帰りも含む)または仕事中に事故に遭った場合には、相手方からの支払を受けるほかに、労災保険から治療費や休業損害の支払をうけることができます。
相手方からの支払と、労災保険からの支払の両方からの支払を受けることができる場合、どちらから支払を受けるほうが有利なのか、相談を受けることがあります。
労災保険には、相手方(相手方が加入する任意保険会社)から支払を受けるのと比べ、次の利点があります。
また、相手方から支払を受ける場合でも、労災保険に申請することで、特別支給金の支払を受けることができます。
2 過失相殺の影響を受けないこと
交差点での出会い頭の衝突事故などのように、事故の各当事者に過失があるとされる場合、被害者が加害者から支払われる賠償額は、被害者が負う過失割合(事故に対する責任割合)に応じて、減額された金額となってしまいます。
これに対し、労災保険から治療費や休業補償の支払を受ける場合には、過失割合による減額はないので、被害者にとって有利となります。
3 治療費の支払が打ち切られる心配が無いこと
保険会社から治療費の支払を受ける場合、これは、事故の相手方が支払うべき賠償金の前払となります。
相手方は、示談での合意や判決などにより、支払うことが確定した金額を支払う義務がある一方、確定する前に、どの程度前払をすべきかについての決まりはなく、前払の義務を負うものではありません。
このため、相手方の意向次第で、前払である治療費の支払を止めてもよいことになります。
これに対し、労災保険から治療費を支払ってもらう場合には、治療の途中で治療費の支払を止められるおそれはありません。
この点でも、労災保険からの支払の方が被害者にとって有利です。
4 特別支給金の支払があること
労災保険からの支払の中には、相手方からの賠償金と同じ、損害に応じて支払われる部分と、これとは別に支払われる特別支給金と呼ばれる上乗せ部分があります。
相手方から支払われる部分は、損害に応じた支払だけであり、上乗せ部分はありません。
このため、労災保険を申請することで、賠償金とは別の、上乗せ部分の支払を受けることができます。
また、相手方から賠償金の支払を受けた場合、同じ損害について重ねて労災保険から支払を受けることはできませんが、特別支給金については、相手からの支払の有無にかかわらず支給されます。
5 労災保険のデメリット
申請する際に、申請書類にお勤め先による証明を受ける必要があります。(労災保険の申請者が、お勤め先の従業員であることなど)
会社が労災保険の手続きに消極的な場合、労災保険の手続きが難航することがあります。
また、労災保険の支払項目の中に、慰謝料に相当する支払項目はないので、慰謝料については、事故の相手方に請求する必要があります。
6 まとめ
事故に遭った場合、相手方に賠償請求するほかに、保険の利用によって、より良い結果を得ることができる場合があります。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
収入の減少がない場合の逸失利益について
1 はじめに
自賠責保険により後遺障害が認定されると、後遺障害を理由とする慰謝料のほかに、逸失利益についての賠償が問題となります。
逸失利益とは「後遺障害により労働能力が低下し、これが原因で収入が減少したことに対する賠償」のことです。
それでは、無収入の場合や、「収入の減少」がない場合に、逸失利益に対する賠償を請求することができるのでしょうか。
2 無収入の場合
現在無収入であっても、将来収入を得ることが見込まれるのであれば、将来収入を得ることを前提として、逸失利益に対する賠償を請求することができます。
就労前の若年者(学生など)や、事故に遭ったときは無職だったが、その後の就職が内定していた場合などです。
世帯での家事労働に従事している場合にも、女子平均賃金を基準とした収入の減少が生じたものとして、逸失利益に対する賠償を請求することができます。
これに対し、無職の高齢者や、就労(家事労働を含む)していない方が、就労の目処が立っていない状態で事故に遭った場合には、将来収入を得ることが見込まれない、即ち労働能力の低下があっても収入の減少が生じたものとは認められないため、逸失利益に対する賠償請求は認められないことになります。
3 減収がない場合
裁判で最も問題になりやすいのが、後遺障害が認定された後も、収入の減少がない場合に、逸失利益に対する賠償請求をすることができるかという問題です。
逸失利益は「労働能力の低下により収入が減少したこと」なので、後遺障害による労働能力の低下があっても、収入が減少しなければ、逸失利益は認められないことになります。
実際、比較的収入が安定している公務員の方が逸失利益を請求したことに対し、これを認めない裁判例が複数あります。
これに対し、収入の減少が生じない理由が、被害者本人の努力や周囲の援助による場合、今は下生しなくても将来の転職などにより不利益を被ることが予想される場合、将来の昇進に影響がある場合などには、逸失利益に対する賠償請求が認められることがあります
「現在、減収が生じてない」ことから直ちに逸失利益が発生していないとするのではなく、将来の不利益や、逸失利益が生じていない事情を考慮することとされています。、
4 まとめ
今回は逸失利益に対する賠償請求についてお伝えしましたが、逸失利益に限らず、後遺障害の賠償請求については、いろいろと難しい問題があることが多いです。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
脊柱の変形の後遺障害について
1 はじめに
事故に遭った後、後遺障害が残ったとして、自賠責保険に対し、後遺障害に対する保険金の支払を申請することができます。
その多くが、頸椎捻挫・腰椎捻挫のけがを負い、治療を継続したものの痛みが残ったとして、後遺障害の保険金の支払を申請するものです。
これに比べ、数は少ないですが、比較的多く見られる後遺障害の申請として、脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)を骨折するけがを負い、これによる変形が残ったとする申請があります。
後遺障害として認定される要件は、レントゲン・CTなどの画像検査により、骨の変形が認められることです。
目に見えない痛みを対象とする頸部捻挫・腰部捻挫の後遺障害と比べると、画像で変形の有無を申請前に確認することができるため、事前に変形があることの確認がされていれば、後遺障害の申請が認められやすいということができます。
2 労働能力喪失率について
脊柱の変形の後遺障害には、後遺障害の申請が認められやすいとの利点がある一方で、頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害と異なり、労働能力喪失率について争いになりやすいとの問題点があります。
脊柱の変形の後遺障害には、脊柱に著しい変形を残すものと、(単に)変形を残すものの2つがあります。
単なる変形については、検査画像において何らかの変形が認められれば、変形の程度を問わず、後遺障害として認定されます。
これに対する労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級表では20%とされており、労働能力の5分の1を喪失したものとされています。
3 脊柱の変形による実際の影響
しかしながら、脊柱の変形が実際の労働能力に及ぼす影響は、被害者によって異なるというのが正直なところです。
変形があったとしてもあまり影響がない方がいらっしゃる一方で、変形による痛み、疲れやすさなどに悩まされる方もいらっしゃいます。
また、建設業・農作業などの身体に対する負担が大きい仕事なのか、事務作業のような比較的身体に対する負担が少ない仕事なのかによっても、変形(後遺障害)の仕事に対する影響は違ってきます。
このため、お仕事の内容と、後遺障害がお仕事に及ぼす影響について、それぞれの被害者の実態に合わせ、明らかにした上で、実際の労働能力喪失率がどの程度なのかについて、立証する作業が必要となります。
4 減収の有無について
脊柱の変形があっても、その影響が少ない場合、仕事への支障がなく減収が生じないことが考えられます。
また、仕事に支障があったとしても、減収しにくい給与体系(身分保障が手厚い公務員の場合など)の場合は、減収が生じないことがあります。
後遺障害が認定された場合、被害者がお仕事に従事している場合であれば、慰謝料の他に逸失利益を請求できます。
しかし、逸失利益は「労働能力が喪失(低下)したことにより、労働により得られる収入が減少したことに対する賠償」であるため、減収がない場合には、後遺障害に対する慰謝料の賠償は認められても、逸失利益についての賠償は認められない場合があります。
被害者が公務員の方の場合、減収がないことを理由に逸失利益の請求を認めないとした裁判例が複数あります。
ただし、減収がない場合でも、これが被害者本人の努力や周囲の手助けによる場合は、逸失利益を認めた裁判の例もあります。
5 まとめ
今回は脊柱の変形による後遺障害の賠償請求についてお伝えしましたが、脊柱の変形に限らず、後遺障害の賠償請求については、いろいろと難しい問題があることが多いです。
専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
ドライブレコーダーの画像データの保存について
1 はじめに
事故に遭った車両にドライブレコーダーが搭載されていた場合、事故の詳細が明らかにすることができます。
この結果、事故において争いとなりやすい項目である過失割合の問題を早期に解決することができます。
ドライブレコーダーのデータは、事故に対処する弁護士にとっても大事なデータとなります。
しかし、残念ながら、ドライブレコーダーを正しく操作することができないことで、事故の詳細を明らかにすることができず、紛争が長引いてしまうことが、しばしば見受けられます。
2 データが上書きされてしまうこと
ドライブレコーダーのデータの保存の失敗で、一番多いのがこのケースです。
ドライブレコーダーを取り付けたことだけに安心してしまい、いざ事故に遭ったとき、どのようにデータを取り出して保存するかについて確認しておく必要があります。
3 記録媒体の紛失
データを保存するところまではよかったのですが、SDカードなどのデータを保存する部品をなくしてしまうケースもあります。
また、部品そのものを保存するだけではなく、別のパソコンやメモリーに保存してバックアップしておくことも大切です。
4 ドライブレコーダー付きの自動車保険に加入する
保険会社によっては、ドライブレコーダー付きの保険を販売しているところもあり、事故があった場合、事故時の画像が自動で保険会社に送信される設定となっているとのことです。
このような保険であれば、データの保存に失敗することがなく、機械の操作に慣れていない方にとっては安心です。
5 音声を録音できるようにしておくこと
保存するデータの節約のためかもしれませんが、ドライブレコーダーの機種によっては、画像の記録のみであり、音は記録されなかったり、音を記録しない設定が可能となっているものがあります。
画像と音は、両方記録できるようにしておくことが大切です。
例えば、合図を出していたか(ウインカーを点滅させたか)により、運転者の責任の有無・割合が変わるケースがあるのですが、録音できる状態であれば、ウインカーの点滅音が録音されるので、合図を出したことの証拠とすることができます。
また、後遺障害の認定に当たっては、事故による身体への衝撃の程度が問題となることがありますが、これも、音の有無により、印象が大きく変わると思います。
6 おわりに
費用や手間はかかりますが、いざというときの備えとして、ドライブレコーダーの設置と、その操作・データ保存の方法の確認をすることをお勧めします。
頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害の認定について
1 はじめに
事故によるケガで最も多いケガが、頸椎捻挫・腰椎捻挫です。
そして、治療を継続したが、痛みが残った場合、痛みが残ったことを理由とする後遺障害の申請をすることになります。
しかし、実際のところ、なかなか認定されない傾向にあります。
2 画像検査での異常がないこと
頸椎捻挫・腰椎捻挫は、いずれも、レントゲンやMRIなどでの画像の異常は認められません。
痛みがあるが画像上の異常はないものが「捻挫」と診断されており、もし骨折や組織の断裂などがあれば、捻挫ではなく、〇〇骨折・〇〇断裂などの診断名がつきます。
画像検査の異常がないということは、痛みの原因が明らかにされていないことになるので、後遺障害の認定はされにくくなります。
3 症状の継続
後遺障害が認定されるためには、症状固定、即ち治療終了後も痛み・関節の可動域制限、傷跡などの症状が継続することが要件となります。
症状が継続せず、治ってしまうのであれば、当然のことながら、後遺障害には当たらないためです。
後遺障害の原因が、関節の変形や傷跡など、目に見えるものであれば、症状の継続の有無は比較的判断しやすいと思います。
しかし、痛みは目に見えませんし、先ほどお伝えしたとおり、痛みの原因とされる捻挫も、検査画像での異常が認められない場合に付く診断名です。
では、「痛みの継続」について、どのように判断するかというと、事故の大きさ(車両の損壊の程度など)、治療期間、通院日数、被害者の年齢、治療経過など様々な要素を考慮して判断していくことになります。
4 認定されにくい理由について
一般的な傾向として、車両どうしの事故において車両の損傷が軽微であること(→身体への負荷が小さいと考えられる)、通院回数が少ないこと(→症状が軽いとみられる)、若年であること(→回復力が強いと考えられている)、症状の経過の中に「症状の改善」についての記載があること(→いずれ治癒に向かうと考えられる)は、いずれも、認定されにくい要素となります。
後遺障害が認定されなかった場合に、これに対する異議申立てをしたが、それでも後遺障害が認められなかったケースでは、診療録などに症状の改善についての記載があることが、認定されない理由とされることが多いように思われます。
また、「痛みの継続」は多分に「将来の予測」ということになるので、このことが,認定されにくかったり、認定される事案と認定されない事案との区別がつきにくい理由と思われます。
4 おわりに
後遺障害の認定は、事案によっては難しい問題が生じることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。
加害者が自転車である場合の告訴について
1 はじめに
交通事故を物件事故(物損事故)から人身事故に切り替える場合、被害者が(事故による)ケガをしたことが記載された診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替わります。
しかし、加害者が自転車である事故の場合は、診断書の提出のみでは足りず、告訴が必要とされています。
なぜでしょうか。
2 適用される罪名の違い
自動車(道路交通法2条1項9号の「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」。四輪自動車、バイクなど)及び原動機付自転車による事故において死傷者が生じた場合、多くの場合は、過失運転致死傷罪が適用されます。
同罪の適用に当たっては、告訴は要件とはされていません。
しかし、自転車が加害者の場合、自転車は自動車等には当たらないため、過失運転致死傷罪の対象とはならず、刑法209条1項の「過失傷害罪」が適用されます。
そして、同条2項で、過失傷害罪を適用して処罰するためには告訴が必要となることが規定されています。
このため、加害者が自転車の場合には、告訴が必要となります。
3 告訴の方法について
告訴状の提出が必要となります。
告訴状は、簡単な事例であれば、警察が参考となる文案を示してくれることが多いようです。
また、告訴について規定した刑事訴訟法241条では、検察かまたは警察官に口頭で告訴することができる旨、規定されています。
告訴期間は、犯人(事故の相手方)を知った時から6か月とされていますので、期間を過ぎないように注意してください。
4 告訴をする目的
本来、告訴は相手方の処罰を求める行為ですので、相手方の処罰を目的とする時に告訴すべきです。
しかし、告訴をしたことの効果として、告訴をすることで、事故の状況が明らかになり、これが民事の損害賠償請求に役立つことがあります。
交差点での衝突事故のように、双方の過失の有無・割合が争われることが予想される事故については、事故の状況を明らかにする必要があります。
告訴をし、警察が事故の捜査をした場合、見ることができる範囲は事案により異なりますが、事故の被害者が、警察が作成した書類を確認し写しを得ることができます。
この書類が、損害賠償請求に役立つことがあります。
5 おわりに
告訴については、事案によっては難しい問題が起こることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。
代車特約について
1 はじめに
自動車保険には、本来の保険である賠償責任保険※のほかに、様々な特約があります。
今回は、代車特約について説明します。
※ 賠償責任保険
事故の相手方より損害賠償の請求がされた際、保険会社が被保険者(保険契約に基づき、保険から保険金の支払を受けることができる者)に代わり、または被保険者が相手方に賠償金を支払ったあと、当該賠償額を支払ってくれる保険をいいます。
相手方の車両が破損したときの修理費、ケガをしたときの治療費などが保険会社より支払われます。
2 代車特約とは
事故後、被害者が車両の修理期間または新たな車両を買い替えるまでの期間の代車費用について、被害者が契約する保険会社より支払われる保険です。
多くの契約では、日額〇〇円×最長30日までなどと、日額と支払可能期間が定められています。
3 代車特約を使用することのメリット
事故により発生した損害について、御自身の保険から支払を受けることに対し「自分の保険を使いたくない」「相手方から支払うべきだ」などとして、否定的な考えを持つ方が少なからず見受けられます。
しかし、相手方からではなく、被害者自身の保険から支払を受けることについて、以下のようなメリットがあります。
また、一般的には、特約の使用のみでは保険料の値上がりはありません。
⑴ 過失相殺の影響がないこと
交差点での事故のように、双方に過失割合が発生する事故の場合、相手方から代車費用の支払いを受ける場合には、本来の代車費用から過失割合分を減額した金額の支払いとなります。
例えば、被害者の過失割合が1、相手方9、被害者に発生した代車費用が10万円の場合、相手方からの賠償額は、1割減の9万円となり、減額された1万円について被害者が負担することになります。
これに対し、代車費用特約より支払を受ける場合には、保険契約において「被害者が重過失の場合は保険金を支払わない」などの特約がある場合を除き、被害者の過失割合の程度にかかわらず、過失相殺されていない所定の金額が支払われます。
⑵ 相手方(相手方の保険会社)との紛争を避けることができること
代車費用については、代車の使用期間を巡り、賠償の対象となるのはどの期間までかが争いとなることがあります。
例えば、諸般の事情により、修理の開始が遅れた場合、開始が遅れた期間の代車費用について、相手方が賠償を拒むことがあります。
このような場合、代車費用特約があれば、相手方が支払を拒んでいる分について、代車費用特約から支払を受けることで、紛争や被害者の損害を回避することができます。
4 おわりに
必要な特約を備え、活用することで、事故の被害を回避したり軽減することができる場合があります。
専門家である弁護士にご相談ください。
被害者が加入する保険の使用について
1 はじめに
事故の被害に遭われた場合、相手方が任意保険に加入していれば、相手方の任意保険から賠償を受けるのが原則です。
しかし、相手方の任意保険から支払を受けるよりも、被害者が加入する任意保険から支払を受けた方が良い場合があります。
2 過失割合が発生する場合
⑴ 過失割合が及ぼす影響
相手方に追突された事故については、被害者に過失がないとされ、加害者より損害全額の賠償を受けることができるのが一般的です。
しかし、交差点での車両同士の衝突事故など、追突事故以外の多くの事故では、被害者にも過失があるとされ、事故の状況・類型に応じた過失割合が発生することにより、損害額の全部を加害者から賠償してもらえない場合があります。
例えば、修理費が100万円かかった場合、被害者の過失割合が10、相手方の過失割合が90である場合は、相手方より賠償されるのは90万円となり、残り10万円は、被害者が負担しなければなりません。
また、相手の車両の修理費として50万円が発生した場合、相手方に対し50万円の
1割である5万円を支払う義務があります。
⑵ 修理費を被害者の車両保険から支払った場合
被害者が加入する車両保険から修理費を支払う場合には、過失相殺されることはありません。
修理費が相当かどうか、支払われる保険金額の上限による制限はありますが、相手方に支払を求める場合と異なり、過失割合に応じた減額が生じることもありません。
このため、過失割合による減額が見込まれる場合は、相手方に請求するのではなく、被害者が加入する保険から支払をしてもらうことを検討したほうがよいです。
⑶ 保険料の値上がりがあっても、被害者にとって有利な場合
車両保険を使用した場合、保険料が値上がりします。
しかし、例えば、被害者の負担額(過失割合による減額と相手方への支払額の合計額)が20万円、保険料の値上がり額が10万円であれば、保険料の値上がりを考慮しても車両保険を使用したほうがよいことになります。
加入する保険会社に対して10万円を支払う代わりに、保険会社から相手方や被害者自身に20万円を支払ってもらうのと同じことになるためです。
一般的に、負担額が保険料の値上がり額を上回る場合は、保険を使ったほうがお得になります。
⑶ 人身傷害特約(けがに対する支払)、代車費用特約(レンタカーの費用に対する支払)
特約の使用に対しては、保険料の値上がりは生じないことが一般的です。
このため、過失割合による減額が見込まれる場合には、相手方に請求するより、これらの特約から支払ってもらったほうが、過失割合による減額がなく、被害者にとって有利です。
3 相手方の資力が乏しい場合
当然のことではありますが、相手方の資力が乏しい場合、相手方からの賠償金支払は事実上不可能です。
このような場合には、被害者の保険から支払を受けることで、相手方からの支払に代えることができます。
4 相手方との紛争を避ける場合
代車費用(レンタカーの費用)について、代車の必要期間を巡り、争いとなることがあります。
このような場合、代車費用の全部を相手方に請求するのではなく、一部を被害者の保険から支払ってもらうようにすれば、相手方の負担が減るため、争いを避けることができます。
5 おわりに
交通事故の紛争を解決するためには、相手方からの賠償金獲得だけではなく、被害者が加入する保険を活用することが役に立つことも多々あります。
保険の活用も含め、弁護士にご相談されることをお勧めします。