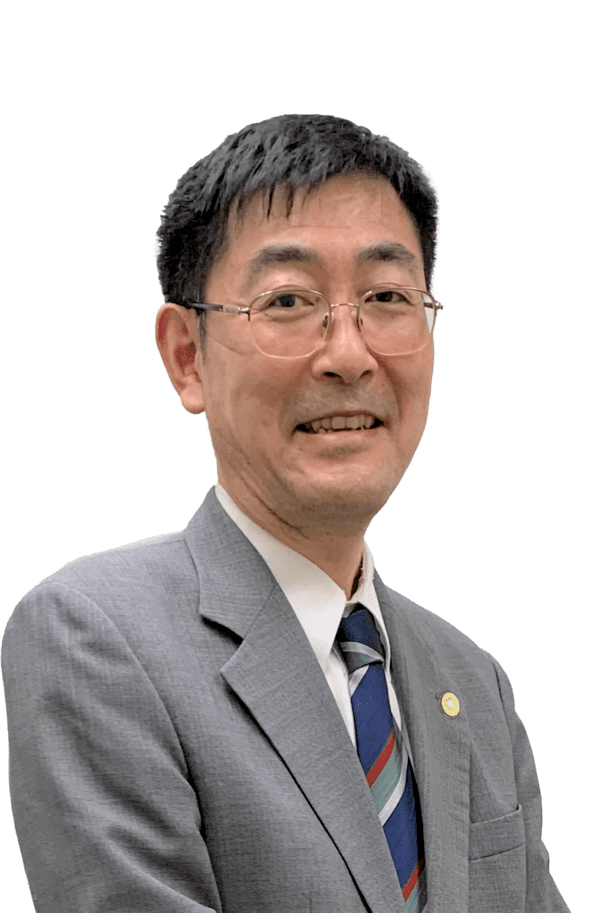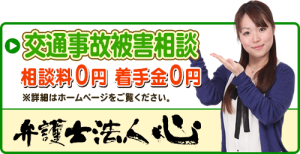ブログ
ドライブレコーダーの必要性について
カテゴリ: その他
1 ドライブレコーダー(以下「ドラレコ」といいます。)が一般車両に搭載されるようになってから、それなりの期間が経ったためか、ご依頼をいただいた案件の中で、ドラレコの画像を見て検討すべき案件が増えてきた感じがします。
ただ、カーナビに比べると、まだ普及の割合が低いような感じがします。
2 自動車事故における、各当事者の責任を明らかにするためには、なによりも事故の状況をきちんと把握することが必要です。
ドラレコが搭載される前は、各当事者の供述と、事故現場に残された痕跡(ブレーキ痕など)及び車両の損傷箇所・状況により、事故状況を判断していました。
このことは、今でも変わらないのですが、供述は、記憶違いや思い込みなどにより正確ではない場合がありますし、現場の痕跡は、これがない場合のほうがむしろ多いです。
これに対し、ドラレコは、カメラに収まる範囲ではあるものの、事故の一部始終を明らかにしてくれるので、上記の問題を一気に解決してくれる、画期的なものです。
3 どのような事故でも、ドラレコの画像の正確性は大変役に立ちますが、その中でも主立ったものをあげるとすれば、やはり交差点内での事故かと思います。
相互の車両の動きや、信号表示が記録されることで、事故の状況把握に大変役立ちます。
信号表示については、画像以外の方法により確実な立証をしようとした場合、目撃者の証言に頼るほかありませんが、目撃者がいないことのほうが多いので、ドラレコのあるなしは大きな影響を及ぼします。
4 ただ、残念なことに、運転前に、ドラレコの操作方法を確認していなかったため、せっかく事故の状況が録画されたのに、その後にデータが上書きされてしまい、役に立たなかったという事案が何件かありました。
いざというときのデータの保存方法と取り出し方法は、きちんと確認していただきますよう、お願いします。
また、画像だけでなく、音も重要です。
一例として、ウインカーを出しているかどうかにより、事故の責任割合が異なる場合があります。録音がオンとなっていれば、ウインカーの点滅音が記録されるので、ウインカーを出していたことの立証ができますが、オフになっていると、この立証ができなくなってしまいます。
ドラレコは、録画だけではなく、録音もできる状態で使用してください。
5 私たち弁護士としては、事実をきちんと把握した上で、法に従った適切な解決方法を見つけることをモットーにしています。
ドラレコは、上記のために必要不可欠な機器であることを理解していただけると幸いです。
症状固定日について
カテゴリ: その他
1 症状固定の意味
症状固定とは,治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいいます。
一般的には,後遺障害診断書に医師が記載した症状固定日をもって,症状固定日とされますが,裁判等において,相手方がこれと異なる日を主張したり、裁判所が上記記載と異なる判断をすることもあります。
2 症状固定日が問題となる理由
上記のように,症状固定日について争いとなる理由は,交通事故の加害者としては,原則として症状固定日までの医療費を負担すれば足り,同日よりも後の医療費を負担する義務はないことによります。
症状固定は「治療を続けても症状の改善が見込まれない状態」ですので、この後に医療費を費やしたとしても治療効果は見込めず、そのような無益な費用を加害者(相手方)に負担させるべきではないことによります。
また,入通院慰謝料についても,事故発生日から症状固定日までの期間を前提に算定することとされているため,より手前の日について症状固定日であるとされたほうが,加害者にとって有利となります。
3 どの日を症状固定日とするかについて
上記のとおり,症状固定とは治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいうことから,症状固定日は,上記状態に達した日,ということになります。
しかしながら,症例の多くは,徐々に症状の改善が進み,ある一定の時期に,受診を継続するも,改善が見込まれない状態になるという経過をたどります。
症状固定か否かの判断については,その性質上,これより前の状態と比較しながら判断するしかありません。
このため,ある日を境として急に症状固定に至るということはまずありませんし,症状固定とするか否かにつき見極めるための一定の期間を要することについても,やむを得ないものと考えます。
4 被害者として留意すべきこと
症状固定の判断に際しては,症状の改善の推移が把握できることが前提となります。
このため,むやみな転医は避けてください。
また,頸椎捻挫などのように,外部から症状を把握しづらい症例については,ご自身の症状について,なるべく正確に医師に伝え、これをカルテ(医療記録)に記載しておくことが,症状固定の状態を正確に把握するために必要となります。
ただ漫然と診察を受け続けるのではなく、ご自身の状態を、医師に伝え記録に残してもらうように心がけてください。
事件と弁護士費用
カテゴリ: その他
1 事件解決を弁護士に依頼する際、その費用として真っ先に皆様が思い浮かべるのは、弁護士に対する報酬(以下「弁護士報酬」といいます。)ではないかと思います。
実際、これから述べる事件解決に必要な費用のうち、弁護士報酬が大きな割合となるのは確かです。
2 しかしながら、契約する弁護士や事務所の方針にもよりますが、実際には、事件解決までに、弁護士報酬以外にも、以下のような費用が発生します。
⑴ 書類作成、送付に係る費用(コピー代、郵送費用など)
⑵ 現場や裁判所などへの移動に際しての交通費、日当
⑶ 事故の状況図作成や専門家の意見に基づく文書を作成する際、外部機関(調査会社など)に支払う費用
上記の費用のうち、⑵及び⑶は、相手方との協議がうまくいかず、裁判所に対する訴えを提起した場合に発生することが多く、逆に話し合いにより解決できるのであれば、⑴のみか、⑶のうち現場確認とその図面作成のための費用(例えば、事故現場において、事故関係者による事故の状況についての説明に基づき、事故の状況図を作成する場合など。事案にもよりますが、数万円程度。)くらいで済みます。
しかし、裁判となり長期間争われる場合には、裁判の期間に応じて、その費用は増えることとなり(裁判を続けることによる書類の費用や、裁判所への出頭費用が増加するため。)、⑶のうち専門家の意見に基づく文書を作成する場合は、数十万円あるいはそれを超える費用を要する場合があります。
「裁判には時間とお金がかかる」のは事実であり、これを避けるために、裁判にまで至る前に話し合いによる解決に向けた努力がされるわけです。
3 また、一定の結論を得るに当たり、高額であってもその費用の支出が不可欠となる場合があります。
上記⑶の図面や文書の作成にかかる費用がそれであり、その内容が事件の結論を左右することがあります。
私が経験した裁判の事例では、通常の玉突き事故(通常は死亡にまで至ることがない事故)であるにもかかわらず、事故の数日後に被害者が死亡したところ、その死因を巡り、事故が原因なのか、それとも被害者の持病である心臓疾患が原因であるのかが争われた事例がありました。
上記の死亡原因について、地裁は事故が原因であるとしましたが、高裁において、心臓疾患による死亡としても被害者の身体の状況(解剖結果)と矛盾しないとの専門家の意見書を提出したところ、裁判所もこれを認め、最終的な解決となりました。
この事例では、専門家の意見書が解決に不可欠であったわけですが、そのために高額な費用を要したことも事実であり、当該費用の支出なくしての解決は見込めない事案でした。
4 このように、紛争解決までには、弁護士に対する報酬以外にも様々な費用がかかります。
また、事件解決のためには、弁護士報酬のみならず、上記3のような、専門家への費用支払が必要となる場合もあります。
事件解決のために一定の費用を要する場合、これを支払うことができない場合は、正しい結論が得られないという事態もあり得ます。(上記3の事例で、専門家の意見書が提出されなかった場合など。)
5 そこで、ご加入の保険契約に弁護士費用特約がある場合には、ぜひ加入されることをお勧めします。
弁護士に依頼する際の費用負担が避けられるだけではなく、事件解決に必要な費用の備えにもなるためです。
依頼を受ける弁護士の立場としても、事件解決に必要な費用が工面できず、本来得られるべき結論が得られないような事態は、できれば避けたいものです。
「適切な解決を得るための備え」として、弁護士費用特約への加入をご検討いただければと考えます。
過失割合について
カテゴリ: その他
過失割合について
1 過失割合とは何か
過失割合とは、事故に対する、当事者双方の責任の割合を示したものになります。
全体の責任割合を10あるいは100として、そのうち各当事者がどの程度の責任を負うべきかが示されます。
例えば、A車とB車が衝突し、各運転手に50万円の損害(治療費)が発生した事故において、過失割合がA車とB車共に50(過失割合の合計は100)とされた場合は、A車とB車は、共に、相手方に対し25万円(=50万円×50÷100)を支払えば済むことになります。
A車が0、B車が100(B車のみが責任を負う事故)であれば、A車は50万円の治療費の全額を賠償してもらえるのに対し、B車は、相手方からの賠償を受けることができず、治療費は自分で負担しなければならないことになります。
2 過失割合の定め方
交通事故は、これまでに多数の事故が発生し、かつ、これに対する裁判所の判断が積み重ねられてきています。
同じ類型や態様の事故であるにもかかわらず、裁判所ごとに判断が異なっていたのでは、不公平になります。
このような事態を避けるために、事故の類型ごとに、過失割合がどうなるかについてまとめられた書籍が発行されています(判例タイムズ社発行の「過失相殺率の認定基準」)。
この書籍は、法律そのものではありませんが、交通事故を専門的に扱う裁判所の部署に属する現職の裁判官が作成に携わっていることから、実際の裁判における一般的な基準として用いられています。
また、その前段階での事故当事者間の交渉や、保険会社とのやりとりなどにおいても、上記書籍を基に過失割合が検討されており、過失割合を検討するにあたり必須の資料となっています。
3 過失割合の修正
もっとも、全ての事故が、上記書籍に記載されたいずれかの類型に該当するとは限りません。何事にも、例外は存在します。
このような場合は、過去の裁判例を調べたり、比較的似ていると思われる類型の過失割合と比較しながら、検討していくことになります。
また、ある類型に該当していたとしても、著しい速度違反があるなどして、標準的な過失割合が変更される場合があります(例えば、本来はAが20、Bが80の過失割合であるところ、Aに著しい速度違反がある場合、Aを30、Bを70とする場合など。)。
過失割合について一定の類型化がされていますが、なお、個々の事故の態様に応じて個別的に検討すべき必要性が全くないというわけではありません。
また、速度超過の有無や、事故発生時の信号の表示が何色であったか(青なのか、赤なのかなど)といった、過失割合の前提である事実の有無それ自体を巡り、深刻な争いとなることも珍しくありません。
4 まとめ
一定の類型化がされているとはいえ、過失割合についての判断には、様々な検討を要する場合があります。
お困りの場合は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
交通事故における示談の際の基準について
カテゴリ: その他
1 交通事故のあと、保険会社から示された示談金の額が妥当な額であるかについてご相談を受ける際、相談者の方より「弁護士基準で示談できるか?」といったご質問を受けることがあります。
ネットなどでは、示談に際し、異なるいくつかの基準があるとしているものがあるようです。
2 しかしながら、何らかの区分がされた基準があるわけではありません。
順を追って説明すると、以下のとおりとなります。
⑴ まず、基準となるのは、裁判となった場合の基準です。
交通事故は、他の類型の事件に比べ、日本全国、多数の 事故が発生し、事件同士の比較が可能な事件といえます。
このような事件において、裁判所の考え方次第で、同じような事故であるにもかかわらず、異なる判断がされたのでは、不公平になってしまいます。
そのため、事故の態様に応じた過失割合や、通院期間や後遺障害の程度に応じた慰謝料の目安が考案され、公刊されています。
赤本と呼ばれる、赤い表紙の本が代表例ですが、この本については、少なくとも東京周辺の裁判所、弁護士事務所及び保険会社に参照され、交通事故の解決に携わる者であれば、必ず把握すべき内容となっています。
⑵ しかし、上記の基準は、あくまで裁判になった場合の基準であり、示談が成立する場合は、裁判の基準よりも若干減額された金額となることが通常です。
これは、お互いが譲歩して早期解決を図るという示談の性質のほかに、裁判における基準が、最後の手段である裁判にまで至ったことによる、労力や時間を要したことを考慮して定められているため、裁判の手前で無事解決したのであれば、その分を減額すべき、との考えによるものです。
⑶ これらとは別に、自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)による基準があります。
自賠責の保険金支払基準は、自動車事故に対し最低限の保障を行うとの自賠責制度の目的のため、上記の各基準よりも低い金額にとどまるのが一般的です。
ただし、同保険の特殊な規定として、原則として過失相殺はしない、過失相殺がされる場合でも一般的な過失割合よりも低い割合での減額にとどめるとの規定があるため、被害者側の過失割合が高い場合には、過失相殺を考慮した一般的な示談の基準よりも、同保険の基準により算定した金額のほうが高くなることがあります。
3 ネットで見受けられる弁護士基準は、多くは⑵の場合を指すようですが、なぜ、このような呼び方ができたかというと、弁護士が関与しない状態で、一般の方が保険会社相手に示談を求めた場合、⑵よりも低い金額か、場合によっては最低基準である自賠責の基準に基づく金額しか示されないことが多いところ、これが、弁護士に依頼することにより、⑵の金額に増額される場合が多いことから、この増額後の金額に対し「弁護士基準」との呼ばれ方が生じたのではないか、と考えます。
本来は、弁護士関与の有無にかかわらず、自賠責の基準ではなく、一般的な示談の基準で示談がされるべきです。
しかし、一般の方々が「どの程度が妥当な金額か」を書物やネットの知識だけで判断することは難しい一方、保険会社は、被害者に対する支払をなるべく抑えたいと考えることから、上記のような現象が起きてしまっています。
4 保険会社から示された示談金が妥当かについて、ご相談を受け、当方が対応した結果、増額されたケースが複数あります。
最近のケースでは、当初提示額は300万円弱であったものが、一般的な示談の基準により算定し直し、提示した結果、1000万円を超える金額にまで増額され、無事示談することができたケースがありました。
保険会社から示談金が提示された場合、弁護士にご相談することをお勧めします。
相手方保険会社からの治療費支払い打ち切りについて
カテゴリ: その他
1 弁護士として交通事故の事件を担当している中で、よくある相談が「相手方の保険会社より、治療費の支払を打ち切るとの連絡(以下「打ちきり連絡」といいます。)が来た。どうしたらよいか。」というものです。
今までは、保険会社が医療費を支払っていたので、被害者による治療費の支払は必要なかったのに、これが打ち切られてしまうと、治療が受けられなくなってしまうのではないか、と心配される方もいるようです。
2 まず、結論から申し上げますと、打ちきり連絡に対し、法的に対抗できる手段はありません。
相手方あるいはその保険会社には、最終的に必要な賠償額を支払う義務や、判決となった場合、あるいは被害者との間で遅延損害金についても支払うことが合意された場合には、損害元金の他に遅延損害金を支払わなければならないという義務はあるものの、これを常に前倒しで支払わなければならない義務があるとまではいえないためです。
ただし、「全て損害額が確定した後で支払う」としたのでは、多くの被害者が困窮してしまうのも事実であり、相手方保険会社が治療費を支払う目的の一つに、被害者保護という目的があることは間違いありませんが、このほかに、その後の交渉を円滑に進めるために支払う、という目的もあります。
保険会社からの治療費の支払は、法的義務というよりは任意のサービスと捉えた方が実態に即していると思います。
3 唯一、強制力のある法的手段として、裁判所に仮処分の申立てをし、判決が出る前に仮に支払えとの決定を出してもらう、という方法があります。
しかし、この方法は、一般の方がご自身で行うには負担が重いこと、判決よりは早い解決を目指すこととされてはいるものの、裁判所の判断が出るまで一定の時間を要することからすると(事案にもよりますが、数か月程度はかかることが多いです。)、速効性や実効性のある方法とはいえないと考えます。
4 そこで、打ちきり連絡がされた場合、一般的にとる手段は、次のとおりとなります。
⑴ 主治医に、治療継続の必要性や、今後の治療期間の見通しなどを記載した診断書を作成してもらい、これを相手方保険会社に提出し、打ちきりについて再検討してもらう。
⑵ 「あと1か月」などと期間を区切って、相手方保険会社からの治療費支払期間を延長してもらう。
打ち切り連絡がされる理由の一つに、何らのめどもないまま治療期間が継続することを防ぎたいという目的があり、このような場合には、期間を区切っての延長であれば、相手方保険会社が延長に同意することがあります。
⑶ 上記⑴、⑵による延長がされない場合は、ご自身の保険(健康保険、労災保険及び人身傷害保険のいずれか)を使って通院をすることになります。
保険を使わずに、被害者自身が医療費を支払い、その後にこれを加害者あるいは自動車賠償責任保険に請求することもできないわけではありませんが、一時的にせよ、被害者自身が費用を支払うことにより、被害者の経済的負担が重くなるので、現実的ではないと思います。
上記の各保険を使う場合、注意点は以下のとおりです。
ア 人身傷害保険は、ご自身が加入する自動車保険に人身傷害保険の特約が付されている場合など、ご自身が保険会社との間で人身傷害保険の契約をしている場合に限られます。
保険会社との契約がない場合は、人身傷害保険は使用できません。
イ 労災保険は、お勤めになる会社の勤務中あるいは通勤途中の事故についてのみ使用可能であり、これらに該当しない場合は、健康保険により受診することになります。
健康保険が使用できる場合と、労災保険が使用できる場合は明確に区別されており、両方を使うことはもちろん、本来は労災保険を使用すべき事故(勤務中あるいは通勤途中の事故)につき、健康保険を使うことはできませんので、ご注意ください。
ウ 労災保険の場合は、労働基準監督署に所定の書類を提出して申請することになりますが、書類の作成に際しお勤め先の会社の確認が必要となりますので、会社の担当者に確認してください。
また、健康保険の場合は、国民健康保険であればお住まいの市区町村に対し、それ以外の健康保険であれば加入する健康保険組合に対し、「第三者行為による傷病届」(事故によりけがをしたこと、事故の相手方の氏名住所などの届け出)をする必要があります。
そして、これ以外に、事故証明など、他の書類が必要となることが一般的ですが、どのような書類が必要かにつき、市区町村あるいは健康保険組合ごとに異なりますので、健康保険の担当者にお尋ねください。
上記の書類を求められる理由は、医療費の一部を健康保険が負担しますが、これにつき、健康保険から事故の加害者に対し、上記負担分の支払を求めることができるとされており、そのためには、傷病届における記載事項が必要となるためです。
なお、労災保険や人身傷害保険においても、保険から相手方に請求できることとされています。
エ 事故発生日から一定期間が経過した後に健康保険あるいは労災保険を使用する場合、相手方保険会社のみならず、健康保険などにおいても「必要な治療期間を経過している」として、保険の使用を断られる場合があります。
この場合は、自費で治療を継続するか、治療を終了して後遺障害の申請あるいは相手方との賠償額の交渉に移ることになります。
5 打ち切り連絡に対する説明は以上となりますが、お困りの場合は、弁護士にご相談ください。
経済的全損について
カテゴリ: その他
1 交通事故により車両が損傷した場合、修理費用が、事故当時の被害車両の価格を超えてしまう場合があります。
このような状態を経済的全損といいます。
全損とは、対象物が完全に破損してしまったり、損傷の程度が激しいため、修理をして元に復することができない状態を言います。(以下、下記の経済手的全損と区別するため、このような状態を「通常の全損」といいます。)
また、損傷の程度がそれほど激しいものではなく、修理することは可能でも、修理費用が車両の価格を上回る状態を「経済的全損」と呼んで、通常の全損と区別しています。
2 経済的全損との用語は、事故の相手方には被害車両の修理をする義務あるいは修理費用相当額を支払う義務はなく、車両の価格に相当する賠償金を支払えば済むという点で、通常の全損と同じであること、しかし修理をしないという理由が、物理的・技術的な理由ではなく、修理費が車両の価格を上回るという経済的な理由であることから、通常の全損と区別するために名付けられた用語です。
修理費用が車両の価格を上回る場合に、賠償の範囲が車両の価格にとどめられる理由ですが、これは、過度の賠償金の支払や加害者の負担を防止したり、いわゆる「焼け太り」を防ぐためです。
例えば、修理費用が200万円、車両の価格が100万円である場合、被害者としては、100万円の金額があれば、同じ価格の車両を購入して、事故前に車両を使用していたのと同じ状態に復することができるにもかかわらず、200万円の修理費を負担すべきとしたのでは、相手方に必要以上の負担を強いることになります。
また、修理費用について、法的には、実際に修理しなくても費用相当額を請求できるとされていることから、相手方から200万円を取得し、そのうちの100万円で元の車両と同じ車両を購入したのであれば、残りの100万円は、文字どおり利得となり、焼け太りとなってしまいます。
また、日本の裁判の傾向として、「焼け太り」の状態を防ぐことについて、重点が置かれています。
このため、事故により車両が損傷した場合、明らかな全損(「一目全損」の状態)の状態でない限り、必ず、修理費用と車両の価格の双方を確認し、比較することとされています。
3 上記の取り扱いの結果、被害者としては、従前の車両を修理して乗り続けたいと考えても、経済的全損の場合には、賠償額と修理費用との差額を自ら負担するか、修理を諦めるかのいずれの選択を迫られることになります。
そして、このような状態に対する不満が、話し合いによる解決を難しくする場合も見受けられます。
そこで、昨今の自動車保険では、「超過特約」として、修理費が車両価格を上回る場合でも、加害者の保険より賠償金(保険金)を支払うことができる特約がもうけられるようになっています。
また、被害者が車両保険に加入しているのであれば、この保険により、車両の価格を上回る部分の修理費用を補填することも可能です。
4 これまで多数の交通事故に接してきた経験からすると、通常の全損に該当する場合はあまりなく、経済的全損となるもののほうが圧倒的に多数であるのが実情です。
このため、保険料の負担という問題はあるものの、上記の超過特約や車両保険に加入することにより、経済的全損となった場合のトラブルを避けることにつき、検討していただくのが望ましいと思います。
5 交通事故でお困りの際は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
任意保険の必要性について
カテゴリ: その他
1 はじめに
法律上、加入が義務づけられている自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)のほかに、任意保険に入るべきことにつき、自動車免許をお持ちの方は、教習所で教習を受ける際、講義を受けたり、映画を見たりしたことがあるのではないかと思います。
任意保険の必要性について、弁護士としての業務を行う中で経験したことなども踏まえ、お話します。
2 事故に遭った場合の賠償額について
⑴ 保険会社による宣伝では、1億円を超える損害賠償が裁判で認められたなど、賠償額が高額になった事例を引き合いに、任意保険加入の必要性を伝える場合が見られます。
しかし、実務では、1億円を超える賠償額となる事案はまれであり、実務に携わる者としては、少々現実離れしているように思われます。
⑵ むしろ、着目していただきたいのは、自賠責保険における保険額が低いため、必要な賠償額を保険でまかなうことができないことが多い、いう点です。
傷害(けが)のみの場合、自賠責保険の上限額は120万円です。
治療費のみであれば、120万円を超えることは多くありません。
しかしながら、上記120万円には、医療費のほかに、通院交通費、休業損害及び傷害慰謝料(治療期間に応じて発生する慰謝料)などが含まれます。
これらを合わせると、通院のみのけがであっても、120万円の上限を超えてしまう場合がそれなりにあります。
また、死亡(上限3000万円)や後遺障害(介護を要しない後遺障害の場合、後遺障害の程度に応じ、75万円から3000万円)の場合、慰謝料のみであれば足りるかも知れませんが、多くの場合、死亡などを原因として得ることができなかった収入についての損害(逸失利益)について賠償が求められることが多く、慰謝料と逸失利益を合わせると、上限額を超えてしまうことが通常です。
自賠責保険のみでは、賠償に必要な費用をまかなうことはできないのが実情です。
3 示談交渉をご自身でしなければならないこと
任意保険に加入している場合には、ご自身が相手方に賠償する義務が生じた場合、保険会社がご自身の代わりに示談交渉をしてくれるのが一般的です。
交通事故における示談交渉は、低額な事案であっても専門的な知識を要するものがあり、弁護士などの専門家以外の方がご自身で示談交渉をするのは、荷が重いと思われます。
しかし、自賠責保険のみの場合は、自賠責保険には示談交渉のサービスはないため、ご自身で交渉するか、ご自身の費用負担により弁護士などに依頼するなどしなければなりません。
4 保険からの支払が後払いであること
⑴ 任意保険の場合は、被害者に対し、事項発生後直ちに医療費を支払ってもらえるため、加害者のみならず、被害者も、医療費の負担なしに受診することができます。
また、休業損害についても、休業損害証明書の提出がされれば、事前(治療終了前)に支払われることが多いです。
事前に費用を支払ってもらえることで、被害者に安心感を与えることができ、その後の示談交渉をスムーズに進める効果もあります。
⑵ ところが、自賠責保険の場合は、被害者にせよ、加害者にせよ、いったんは自ら費用を支払い、その領収書を自賠責保険に提出した後でないと、医療費などについての保険金支払を受けることができません。
一時的にせよ、医療機関などに支払うべき費用を用意しなければならず、任意保険と違って費用を用意するための負担が生じることになります。
5 終わりに
任意保険には、本体である賠償責任保険(相手に対する賠償金支払のための保険)のほかに、弁護士費用特約をはじめ、様々な特約が付されています。
このうち、一部の特約(加入しておいた方がよい特約)について、前回のブログにて紹介しています。
こちらも併せてご覧いただければと思います。
事故に備えて加入しておくべき保険について
カテゴリ: その他
1 はじめに
毎日多数の交通事故の事件に接していますが、そのほとんどに、強制加入の自動車賠償責任保険と併せ、任意保険が契約されていることが一般的です。
そして、任意保険には、様々な特約があり、保険料の負担を考えながら、どの特約を契約するか、悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
そこで、日々、交通事故の事件に接する中で、加入しておいたほうがよいと思われる特約は、以下の3つです。
2 弁護士費用特約
この特約を真っ先に挙げると、「弁護士としての営業のためでしょう」と言われてしまうのは覚悟の上ですが、やはり、加入したほうがよい特約と考えます。
弁護士費用特約は、弁護士に相談したり、相手方に、交通事故による損害に対する賠償を請求する際の費用を補償するためのものですが、この特約がない場合、請求額が少額の場合には、相手からの取得額が弁護士費用に見合わないため、弁護士への依頼を諦めるといった場合が多いのではないかと思います。
しかし、事件の難しさと、請求金額とは必ずしも一致しません。
請求額が少額であっても、複雑な事項についての検討が必要であるなどの理由により、被害者ご本人のみでは対処できない事案もあります。
一例として、以前に扱った事案では、請求額は15万円程度であるにもかかわらず、この金額が妥当な金額であることを示すために、多数の裁判例を調べ、裁判所の判断の傾向を明らかにする必要があるものでしたが、このような作業は、一般の方には難しいのではないかと思います。
また、弁護士の側としても、弁護士費用特約に基づき受任することにより、一定額の収入が確保できるため、少額の請求事案であっても、受任しやすくなり、結果として、被害者としては、弁護士によるサービスが受けられやすくなるということもあります。
さらに、事案によっては、事故の調査などにつき、高額な鑑定費用を要する場合がありますが、これについても、弁護士費用特約によりまかなうことができたり、修理費や車両の価格について争いとなった場合に、ご自身の保険会社のスタッフより援助を受けられる(例:相手方の示した被害車両の価格が実際の価格より低額の場合、これに対抗する資料を作成してもらうことなど。)といった利点もあります。
加入しておくことにより、損をすることはない特約だと思います。
3 人身傷害特約
この特約は、事故により怪我をしたり死亡したりした場合、相手方から賠償を受けるのではなく、ご自身が契約する保険会社より、その全部又は一部が支払われる特約です。
この特約の利点は、次のとおりです。
⑴ 事故の相手方が自賠責保険に加入していない、あるいは自賠責保険への加入だけなので、本来の損害額を賠償してもらうだけの資力が相手方にない場合でも、上記のとおり、自己の保険契約より、賠償金の全部(医療費など)または一部(慰謝料)が支払われますので、相手方が無資力である場合のリスクを回避することができます。
⑵ 相手方が任意保険に加入し、賠償金を支払う資力について問題はない場合でも、相手方の保険会社が、治療費の支払を途中で打ち切るなどして、十分な補償が受けられない場愛があります。
このような場合、ご自身の保険契約から支払を受けることにより、上記の不利益を回避することができます。
4 車両保険
上記2つの特約に比べ、保険料が高めであることと、使用した場合、その後の保険料が高くなることが難点です。
しかし、多くの交通事故で、過失相殺のために損害の一部しか相手方から支払を受けられないような場合や、修理費よりも車両価格の方が下回ることにより、必要な修理費を相手方より支払ってもらうことができない場合(注)が往々にしてあるところ、車両保険に加入しておけば、必要な修理費を確保できる場合があります。
また、損害賠償の範囲、例えば修理費の額や車両価格を巡り相手方と合意ができない場合、ご自身の保険会社より支払を受けられるのであれば、上記争いを回避することができます。
注: 車両が損傷した場合の賠償の範囲は、修理費と、事故当 時の車両価格を比較して、どちらか安い方を支払えば足りるとされているため、修理費の方が車両価格よりも高い場合には、車両価格分を支払ってもらえるにとどまり、修理費全部を相手方から支払ってもらうことはできません。
5 終わりに
上記の説明を踏まえ、ご自身に必要な保険契約を見直していただければと思います。
車両の評価損について
カテゴリ: その他
1 評価損について
(1)車両の評価損とは、事故後に車両の修理を行い、完了し たものの、「事故に遭い修理を行った」ことにより、これがない同種車両と比べ、市場における車両の価値が低下した場合に、この低下分を事故による損害とするものです。
(2)上記の評価損について、どのように算定するのか考えた場合、多くの方は、事故に遭った車両と、事故に遭っていない車両との販売価格の差額が評価損であると考えるのではないでしょうか。
しかしながら、次にご説明するとおり、これまでの裁判所の算定の方法は、上記とは異なっています。
2 裁判所における評価損の算定方法
(1)裁判所における評価損の算定方法は、そのほとんどが「修理費の1割から3割程度の金額(ただし、事例(新車購入後、まもなく事故に遭ったような場合など)によっては、5割など、上記を超える割合としたものがあります。)を、評価損とする。」というものです。
修理費を基礎としているのは、事故による車両の破損状況が大きいほど、修理費が高額となり、これに伴い、評価損も高額となる。」という考え方によるものです。
上記「1割から3割」について、どのように決めるかについては、初度登録からどの程度年数が経過しているか、高価な車両(外国車、国産の高級車、大型車など)か廉価な車両(軽自動車など)か、走行距離などを考慮する、とされています。
初度登録からの年数が少なく(逆に、3ないし5年を超えると、認められにくい傾向があります。)、高価な車両のほうが、上記の割合は高くなる傾向にあります。
また、多くの裁判例は、事故に遭ったことのみをもって直ちに評価損が発生するとはしておらず、車両の骨格部分に損傷が生じた場合に、評価損が発生するとしています。
骨格部分以外の、例えばバンパなどの部品が損傷したのみであれば、当該部品を交換することにより、事故前の状態に戻すことができるのに対し、骨格部分に損傷が生じた場合には、見た目は修復できても、強度の低下など目に見えない悪影響が残るとされていることによるものです。
(2)評価損の算定方法としては、上記の他に、日本自動車査定協会という一般財団法人があり、この団体が発行する自動車価格の査定書を提出する方法もありますが、多くの裁判例は「金額の根拠が不明である」として、査定書に従った認定はしておらず、上記の「修理費に一定割合を乗じた金額」を評価損としています。
3 裁判所における査定方法の問題点
「事故による車両の破損状況が大きいほど、修理費が高額となる」ことは事実です。
しかしながら、事件処理の際に目にする査定の資料や、日本自動車査定協会のホームページに掲載された査定の方法には、「査定に当たり修理費を確認する」との項目は見当たりません。
査定のための書類には、車両の状態や、過去の損傷箇所(修理歴)の確認についての記載はあるものの、「過去の修理費」についての項目はありません。
「修理費を基礎として評価損を算定する」との方法は、裁判所独自の方法ではないかと思われます。
また、修理費に乗じる割合について、なぜその割合となるのか、基準表のようなものがあるわけではありません。
このため、評価損の額が問題となった場合、過去の裁判例を参照し、似たような事案(車種、初度登録から事故までの年数など)と比較しながら、修理費に乗じる割合を判断せざるを得ません。
上記判断の際、時間や労力を要するばかりではなく、割合についての明確な基準がないことにより、「裁判所方式による評価損の算定」が、非常に不明確あるいは不安定なものであると感じられます。
不動産鑑定のように、全国共通の基準に基づく算定ができればよいのに、と思う次第です。
4 終わりに
評価損の判断に当たっては、過去の多数の裁判例を検索・検討する必要がありますがこのような作業は、一般の方には難しいと思います。
評価損が問題となったときは、弁護士に相談されることをお勧めします。
月別アーカイブ
- 2024年06月(1)
- 2024年05月(1)
- 2024年04月(1)
- 2024年03月(1)
- 2024年02月(1)
- 2024年01月(1)
- 2023年12月(2)
- 2023年11月(1)
- 2023年09月(1)
- 2023年08月(1)
- 2023年07月(1)
- 2023年06月(1)
- 2023年05月(1)
- 2023年04月(1)
- 2023年03月(1)
- 2023年02月(1)
- 2023年01月(1)
- 2022年12月(1)
- 2022年11月(2)
- 2022年09月(1)
- 2022年08月(1)
- 2022年07月(1)
- 2022年06月(1)
- 2022年05月(1)
- 2022年04月(1)
- 2022年03月(1)
- 2022年02月(1)
- 2022年01月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(1)
- 2021年09月(2)
- 2021年07月(1)
- 2021年06月(1)
- 2021年05月(1)
- 2021年04月(1)
- 2021年03月(1)
- 2021年02月(1)
- 2021年01月(1)
- 2020年12月(1)
- 2020年11月(1)
- 2020年10月(1)
- 2020年09月(1)
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
0120-41-2403
お役立ちリンク